2021年11月26日
社会保険料とは?
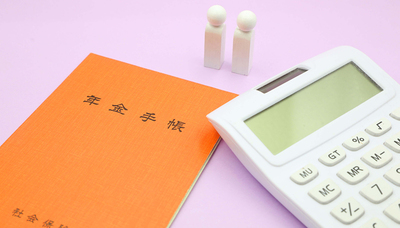
北野純一税理士事務所の南田です。寒さも本格化し、街ではクリスマスの飾りつけが目につくようになってきました。当事務所では、いよいよ年末調整の時期に突入します。年末調整では、年末調整の対象者家族状況の変化などをしっかりとチェックしていきましょう。
年末調整では、「社会保険料」という控除項目がありますが、会計ソフトなどから自動的に入力されたり、証明書の金額をそのまま入力すれば足りるため、税理士事務所ではあまり注目されることのない項目です。しかし、「社会保険」というものは、社会保険労務士という専門家がいることからも分かるように、複雑で広範囲な分野となります。
今回は、社会保険料控除と、そもそも社会保険とは何か、についてお伝えします。年末調整業務を行う際にも、基礎知識があるとイメージしやすくなりますので、参考にしてください。
社会保険とは
「社会保険」と一口にいっても、さまざまな意味で使われ、広義には労働保険制度と社会保険制度を総称して使われます。狭義には、社会保険制度そのものを指す意味で使われます。労働保険制度には、労働保険と雇用保険があり、社会保険制度には年金保険と医療保険があります。
年末調整における社会保険料控除は、「健康保険」「国民健康保険」「厚生年金」「国民年金」「介護保険」「高齢者医療保険」が対象となり、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額が控除できます。自分だけでなく、配偶者や子供などの社会保険料を支払っている場合も、控除することができます。
なお、社会保険労務士の試験においては、労働保険として「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「労働保険徴収法」、社会保険として「国民年金法」「厚生年金保険法」「健康保険法」の6科目に対応しており、広義の社会保険についての知識が問われます。
社会保険と民間の保険との違い
「保険」というと、民間の保険が頭に浮かぶ方も多いと思いますが、民間の保険と社会保険とでは、何が違うのでしょうか。そもそも保険とは、被保険者が支払った保険料をもとに、被保険者に事故や病気などが発生したときに、その事象の発生による損失を埋めるために、その被保険者に給付を行う仕組みをいいます。つまり、「いざというときのための備え」といえます。
社会保険と民間の保険の違いは、運営する主体の違いによるものです。社会保険も民間の保険も、保険者と被保険者が存在し、いざというときに被保険者は保険者から給付を受けることができます。社会保険は政府などの公的な機関が主体となっており、加入が強制的に義務付けられているのに対し、民間の保険は契約による自由な加入となっています。
社会保険に関係する業務
税理士事務所では、社会保険に関係する業務に関わることがあります。税理士事務所は、事業を行っているクライアントとの関わりが深いため、社会保険に関するアドバイスを求められたり、社会保険労務士との窓口になったりしている事務所も多いです。
社会保険に関わる業務のうち、「健康保険や雇用保険、厚生年金などに関する書類作成や労働基準監督署などへの提出の代行業務」「就業規則、労働者名簿、賃金台帳などの労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成」は、社会保険労務士の独占業務となっています。このほかに社会保険に関わる業務には、社会保険に関するコンサルティング業務があります。
近年では、会社と労働者の利害が対立するケースも増えています。労働に関する一般的なアドバイスも、社会保険労務士への窓口も、ある程度の基礎知識がないがないと行うことができません。当事務所のスタッフもクライアントからも頼りにされるべく、日々、社会保険に関する知識を増やしていきたいと思います!
☆高松市の税理士 北野純一税理士事務所ホームページはこちらから☆
Posted by 北野純一税理士事務所 at 10:59│Comments(0)
│日記










